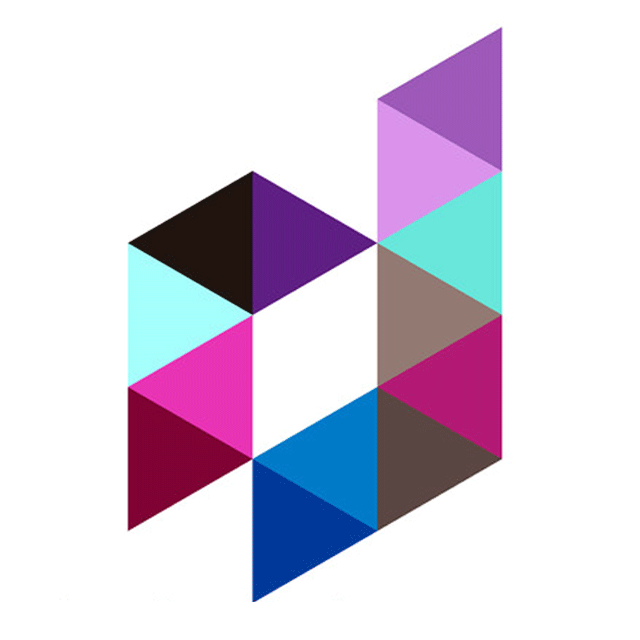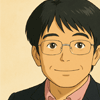上場株式の評価方法(相続・贈与税・申告用)
はじめに
上場株式を相続や贈与で取得した場合、正しい評価を行うことは税務上極めて重要です。株価は日々変動するため、評価の基準日や採用する株価によって課税額が変わることがあります。
この記事では、上場株式の評価方法を整理し、税理士として実務で注意すべきポイントをまとめます。
1.上場株式の評価の基本
上場株式とは、証券取引所に上場されている株式をいいます。
評価の基準日は、相続の場合は被相続人の死亡日、贈与の場合は贈与を受けた日です。
評価額は次の式で求めます。
1株あたりの評価額 × 保有株数
1株あたりの評価額は、次に説明する4つの価格のうち最も低いものを採用します。
2.評価に用いる4つの株価
上場株式の評価では、次の4つの株価を比較して最も低いものを採用します。
- 課税時期(相続開始日または贈与日)の終値
- 課税時期の属する月の毎日の終値の平均額
- 課税時期の前月の毎日の終値の平均額
- 課税時期の前々月の毎日の終値の平均額
たとえば、相続開始日が10月15日の場合、「10月の平均値」「9月の平均値」「8月の平均値」「10月15日の終値」を比較し、最も低い価格を採用します。
3.特別なケースの取扱い
(1)権利落ちなどのある場合
配当や株式分割などの権利が確定する前後で株価が大きく変動する場合には、権利落ち前の株価を採用するなど、適正な評価を行う必要があります。
(2)休日・休場日の場合
評価基準日が土日や祝日など市場の休場日にあたる場合は、その直前の取引日の終値を用います。
(3)複数銘柄を保有している場合
複数銘柄を保有している場合、銘柄ごとに最も低い株価を選ぶことができます。同じ評価月で統一する必要はありません。
(4)株数の確認
株数は証券会社の残高証明書などで正確に確認します。単元未満株や名義株がある場合には注意が必要です。
4.実務上の注意点
上場株式の評価は一見単純ですが、実務では次の点に注意が必要です。
- 株価データは証券取引所や証券会社の公表値を基に確認する
- 休日を挟む場合は評価日の特定を慎重に行う
- 配当や株式分割などの有無を必ず確認する
- 銘柄ごとに最も低い株価を選べることを活かして、全体の評価バランスを考慮する
- 評価の根拠を明確に記録し、後日の税務調査に備える
- 株価変動が大きい時期は、評価時期の選択による課税額の影響をクライアントに丁寧に説明する
5.申告書作成時の留意事項
- 評価計算表や株価データの根拠を添付しておくと、税務署からの照会を受けにくくなります。
- 株式の保有状況や銘柄の内訳を明確に示した一覧表を作成すると、後の確認が容易になります。
- 配当未収や売買途中の株式など、特殊なケースでは証券会社の明細書を添付することが望まれます。
6.まとめ
上場株式の評価は、非上場株式のように複雑な算定は不要ですが、株価の選定には細かなルールがあります。
4つの株価の中で最も低いものを採用する点をしっかり押さえ、評価の根拠を明確に残すことが重要です。
税理士としては、依頼者の財産全体を見ながら、適正かつ節税につながる形で評価・申告を行うことが求められます。