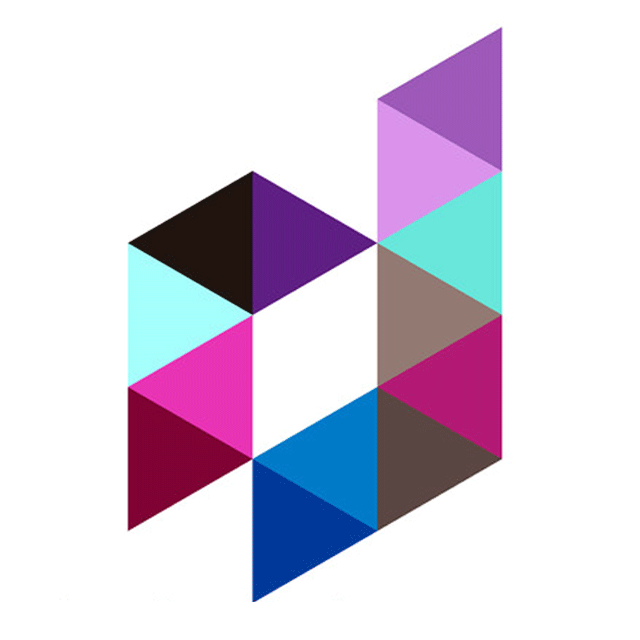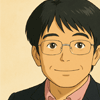導入
相続税の土地評価において、「普通借地権が設定されている土地」は、更地と同様には評価できません。借地権があることで、土地所有者である「底地権者」の権利が制限されているため、評価額は減少します。
この記事では、借地権が設定された土地(底地)の評価方法について、実務上のポイントや計算式を交えてわかりやすく解説します。
借地権付き土地とは?
借地権付きの土地とは、他人(借地人)に貸している土地のことです。通常、「普通借地権」として設定され、借地人が建物を所有し使用しています。
このような土地の所有者(底地権者)は、土地を自由に利用することができないため、評価においては制限を受けた状態で算定する必要があります。
普通借地権のある土地の評価方法
1. 【基本式】底地の評価方法
底地の評価額 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合)
- 自用地評価額とは、土地を自由に使える前提で評価した場合の金額です。
- 借地権割合は、国税庁の路線価図に明示されています(例:60%、70%など)。
【例】
仮に自用地評価額が1,000万円、借地権割合が70%の場合、底地評価は以下の通りです。
1,000万円 ×(1 - 0.7)= 300万円
このように、借地権が設定されていることで、土地の所有権(底地)の価値は下がります。
2. 借地権と底地の両方を評価するケース
相続人が借地権付き土地をすべて承継する場合や、借地権者が同族などで借地権と底地を一体で相続する場合には、両者を別々に評価することになります。
この場合、
- 借地権の評価額 = 自用地評価額 × 借地権割合
- 底地の評価額 = 自用地評価額 ×(1 - 借地権割合)
の両方を相続財産として申告します。
3. 貸宅地として評価する場合(貸家建付地との違いに注意)
借地上に借地人の建物(貸家など)が建っている場合、その土地は貸宅地と評価され、借地権割合を控除する形で評価されます。
ただし、これは借地権が設定されていることが前提です。
賃貸物件があるからといって、常に貸家建付地として評価するわけではない点に注意が必要です。
補足:借地権割合の確認方法
借地権割合は、**国税庁の「路線価図」や「評価倍率表」**で確認可能です。
たとえば、路線価図には「70D」などと記載されており、数字の部分が借地権割合(=70%)を意味します。
借地権割合が明示されていない地域では、原則として60%とされますが、地域性や取引事例によって補正が必要な場合もあります。
実務上の注意点
- 借地権の契約内容や更新状況は、評価に影響する場合があります(例:更新料の支払い、契約期間など)。
- 被相続人と借地人が同族である場合、形式上借地契約があっても実質的に借地権が認められないと判断されることがあります(名義借地の否認)。
- 借地権と底地を併せ持つ場合、一体評価(自用地評価)を検討することもあります。
まとめ
借地権が設定された土地の評価は、自用地評価額に借地権割合を掛けて底地評価を算出するのが基本です。
実務では、契約内容や借地権の実態を丁寧に確認することで、正確な評価と節税対策が可能になります。
借地権のある土地の評価でお困りの方は、相続税に強い税理士にご相談いただくのが安心です。
お問い合わせ
相続税の土地評価に強い税理士がサポートします
借地権や底地の評価でお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。