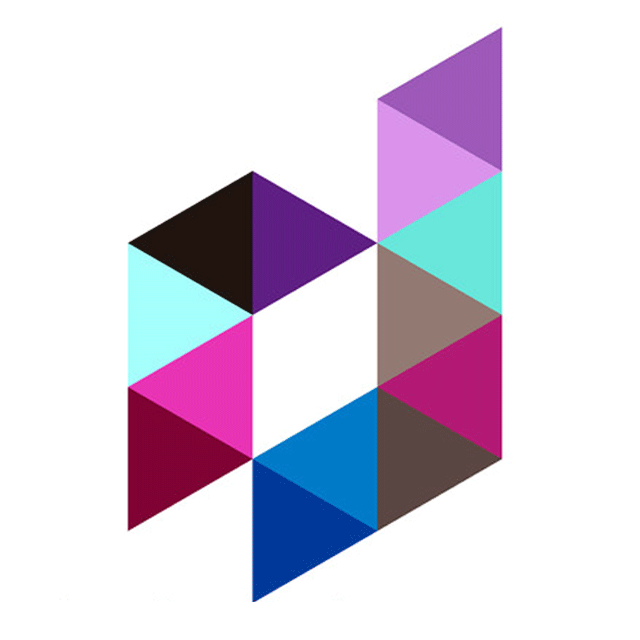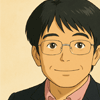【相続税】路線価地域に存する農地の評価方法とは?税理士がわかりやすく解説
相続税の申告において、農地の評価は宅地や山林とは異なる独自のルールがあります。特に路線価地域に存する農地は、「宅地比準方式」によって評価されるため、その正確な理解が不可欠です。
本記事では、相続税法上の農地評価の基本から、路線価方式による評価の実務までを、税理士の視点から解説します。
路線価地域における農地とは?
国税庁が定める「路線価地域」とは、市街地的形態を形成している地域で、道路に対して1㎡あたりの価格(路線価)が設定されている地域をいいます。
この地域に存する農地は、通常の宅地のように「路線価」を基準にして評価するのではなく、農地としての特性を加味して減額される評価方法がとられます。
農地の分類と評価方法
相続税評価において、農地は以下の3つに分類され、それぞれ評価方法が異なります。
| 区分 | 内容 | 評価方法 |
|---|---|---|
| ①純農地 | 市街化調整区域等にある農業専用地 | 農地の固定資産税評価額×倍率 |
| ②中間農地 | 市街化調整区域にあるが、農業以外への転用も可能な農地 | 上記と同様 |
| ③市街地農地 | 市街地的形態をなす区域にある農地 | 宅地比準方式で評価(※本記事の主題) |
この記事で取り上げるのは③の「市街地農地」、つまり路線価地域に存する農地です。
宅地比準方式による評価方法
市街地農地は、「その農地が宅地であったとしたらいくらになるか」を基準にして評価します。これを宅地比準方式といいます。
評価の手順は以下のとおりです。
① 宅地と仮定した場合の評価額を算出
評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 地積
ここで言う「路線価」は、農地が接する道路の路線価です。また、奥行価格補正率はその地形や間口により決定される補正率です。
② 宅地評価額に農地倍率を乗じる
宅地評価額に対して、農業に使用されていることを考慮して、国税庁が定めた「農地倍率(概ね0.7前後)」を乗じます。
評価額 = 宅地評価額 × 農地倍率
この「農地倍率」は、都道府県ごとに異なり、毎年「財産評価基準書」に記載されます。
農地の評価で注意すべきポイント
● 貸付農地の場合は「貸宅地」として評価
農地を他人に貸している場合は、使用貸借なのか賃貸借契約なのかに応じて評価が異なります。賃貸借であれば「借地権割合の控除」が可能です。
● 納税猶予制度の適用可否も要確認
相続した農地については、一定の要件を満たせば納税猶予制度を利用できる可能性があります。後継者の有無や営農継続などが要件となるため、早めの検討が必要です。
まとめ:農地評価は宅地評価とは別の知識が必要です
路線価地域にある農地の評価は、「宅地のように評価してから農地として減額する」という二段階の考え方が必要です。誤って宅地評価のみで申告してしまうと、過大な相続税を支払うリスクもあります。
相続税の農地評価は複雑な計算や地域ごとの倍率など、専門知識が求められます。実務経験のある税理士に相談することで、最適な申告が可能になります。
【関連記事】
- [相続税評価における倍率地域の農地評価方法とは?]
- [農地の納税猶予制度の活用ポイント]
- [農地転用と相続税評価の関係について解説]