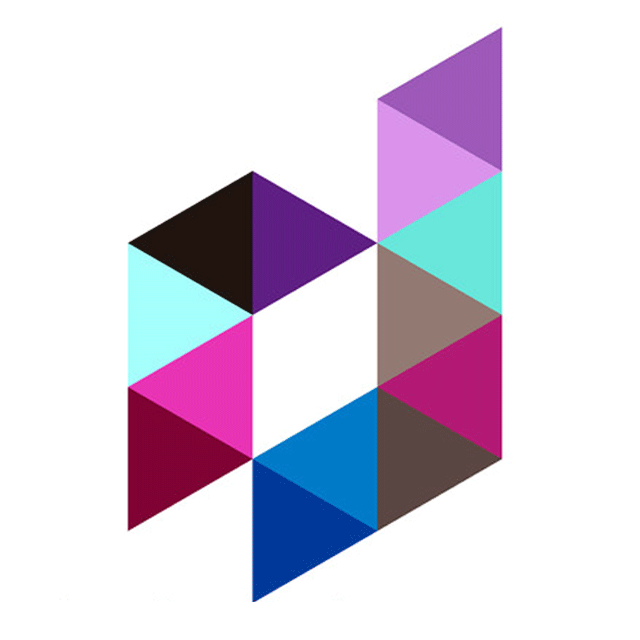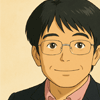【相続税対策】不整形地の評価方法とは?土地評価を正しく行うためのポイントを解説
相続税の申告において、被相続人から引き継いだ土地の評価は非常に重要なポイントです。中でも、土地の形がいびつな「不整形地」の場合は、評価方法に注意が必要です。
この記事では、税理士としての視点から、不整形地の定義、評価方法、評価上の留意点などを解説します。土地の評価を適切に行うことで、相続税を正しく、時に有利に申告することが可能です。
■ 不整形地とは?
不整形地とは、道路に対する間口が狭かったり、奥行が極端に長かったり、鋭角・曲線部分が多く整った四角形などではない土地をいいます。
具体的には以下のようなケースが該当します:
- 三角形や台形の土地
- 奥行が極端に長い旗竿地(路地状敷地)
- 曲がった境界線を持つ土地
- 隣地の影響で利用が制限される土地
こうした土地は、整形地(きれいな長方形や正方形の土地)と比較して利用価値が劣るため、その分評価額が下がる傾向にあります。
■ 不整形地の評価方法
不整形地の評価は、路線価方式を使って行われることが多く、その際に「不整形地補正率」を適用します。
▼ 不整形地補正率とは?
国税庁の定める補正率表に基づき、土地の形状や間口、奥行などに応じて評価額を補正する制度です。
不整形地補正率は以下の要素によって決まります:
- 土地の奥行距離と間口距離の比率(奥行長大・短小)
- 側方や奥行のかげ地割合
- 路地状敷地の割合
- 利用制限の程度(例:建築面積の制限など)
補正率はおおむね0.95〜0.60程度の範囲で、整形地と比べて評価額が5%〜40%ほど下がるケースもあります。
■ 評価例(イメージ)
たとえば、以下のような土地があった場合を考えます。
- 路線価:200,000円/㎡
- 地積:100㎡
- 不整形地補正率:0.80(旗竿地)
評価額 = 200,000円 × 100㎡ × 0.80 = 16,000,000円
整形地と比べて400万円も評価額が下がることになります。
■ 不整形地の評価で注意したいポイント
1. 形状や寸法の正確な把握
測量図や現地調査をもとに、正確に形状を把握することが重要です。評価ミスを防ぐためには、境界確定もできていると望ましいです。
2. 補正率の適用ミスを避ける
不整形地の補正率の選定は、評価の難所です。見た目だけで判断せず、国税庁の「財産評価基本通達」や評価明細書を確認しましょう。
3. 地積規模の大きな宅地との併用
地積が一定以上ある場合、「地積規模の大きな宅地の評価」制度と併用されるケースもあるため、併用可能かどうか検討が必要です。
■ 税理士による評価サポートの重要性
不整形地の評価は、実務上の判断や経験が問われる難しい分野です。評価を誤ると、相続税の過大申告または税務調査リスクにつながる恐れがあります。
税理士が適切に現地確認・資料確認を行い、正しい補正率を用いることで、節税にもつながります。
■ まとめ
不整形地の評価は、相続税の申告において重要な要素の一つです。不整形であるがゆえに評価が下がることは、相続人にとって有利に働くケースもあります。正確な評価を行うためには、税理士による専門的な判断が必要不可欠です。
相続税評価で不安な点がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。