【相続税】調整区域にある雑種地の評価方法とは? 税理士がわかりやすく解説!
相続財産の中に「調整区域にある雑種地」が含まれていた場合、その評価方法に戸惑う方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続税申告における調整区域の雑種地の評価方法について、税理士の視点からわかりやすく解説していきます。
◆そもそも「雑種地」とは?
雑種地とは、「宅地」「田」「畑」など、他の地目に該当しない土地のことを指します。
具体例としては、駐車場や資材置き場、空き地などが挙げられます。
この雑種地が都市計画法上の「調整区域」にある場合、利用用途が制限されるため、評価にも独特の配慮が必要です。
◆「調整区域」とは?
市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を防ぐために指定されたエリアで、原則として建築物の建築や開発行為が制限されています。
つまり、自由な宅地開発ができず、土地としての利用価値が制限されていることが多いのです。
◆評価方法の基本方針
調整区域の雑種地を相続税評価する場合、次のような手順で進めます。
【1】近傍宅地比準方式を検討
評価の原則は**「近傍の宅地の評価額をもとに補正を加える」**方法、すなわち「近傍宅地比準方式」が基本です。
≪手順≫
- 近傍の宅地(なるべく同じ区域内で、利用状況・周辺環境が類似するもの)を探す
- その宅地の評価額(路線価や倍率など)を調べる
- 雑種地の利用状況に応じて「補正率」を掛ける
【2】宅地並み評価が難しい場合は「倍率方式」も検討
調整区域で、周辺に宅地が少なく比準が難しいケースでは、倍率方式(固定資産税評価額 × 地目ごとの倍率)での評価も認められます。
ただしこの場合も、現況が駐車場や資材置き場など特定の利用をしているかどうかによって、補正が必要になることがあります。
◆実務上の注意点
- 建物の建築ができるかどうか(=開発許可の有無)は評価に大きく影響します
- 地元自治体の都市計画課に確認して、用途制限の程度を把握しておくと評価の裏付けになります
- 固定資産税評価額が低く設定されている傾向があるため、そのまま倍率方式を使うと評価額が過小となる恐れも。税務署から指摘を受けることもあるため注意が必要です
◆まとめ
調整区域にある雑種地は、その利用制限の強さから評価に慎重さが求められます。
「宅地並みの評価が可能かどうか」「近傍地が見つかるか」「現況の使用状況」など、さまざまな視点で検討し、正確な評価方法を選択することが重要です。
相続税の土地評価は、専門性が高く、誤ると税務調査のリスクも。
お悩みの方は、ぜひ専門の税理士にご相談ください。
\ 無料相談受付中 /
相続に関するお悩みや、土地の評価についてのご相談は、当事務所までお気軽にどうぞ!
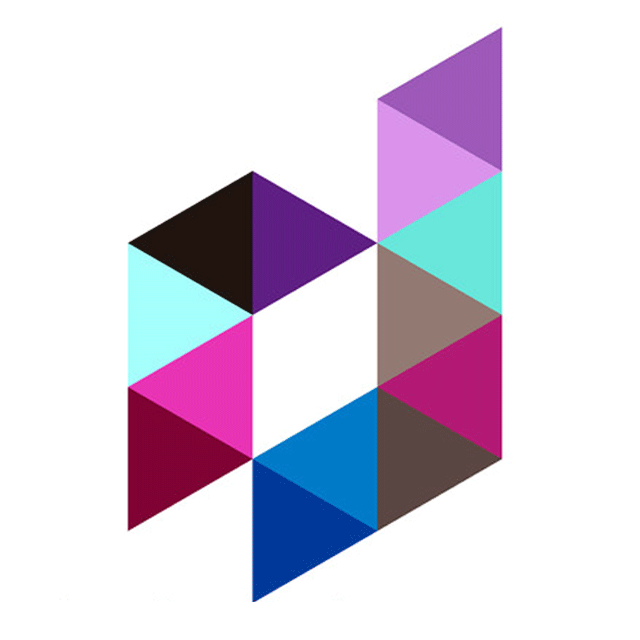

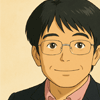
コメント